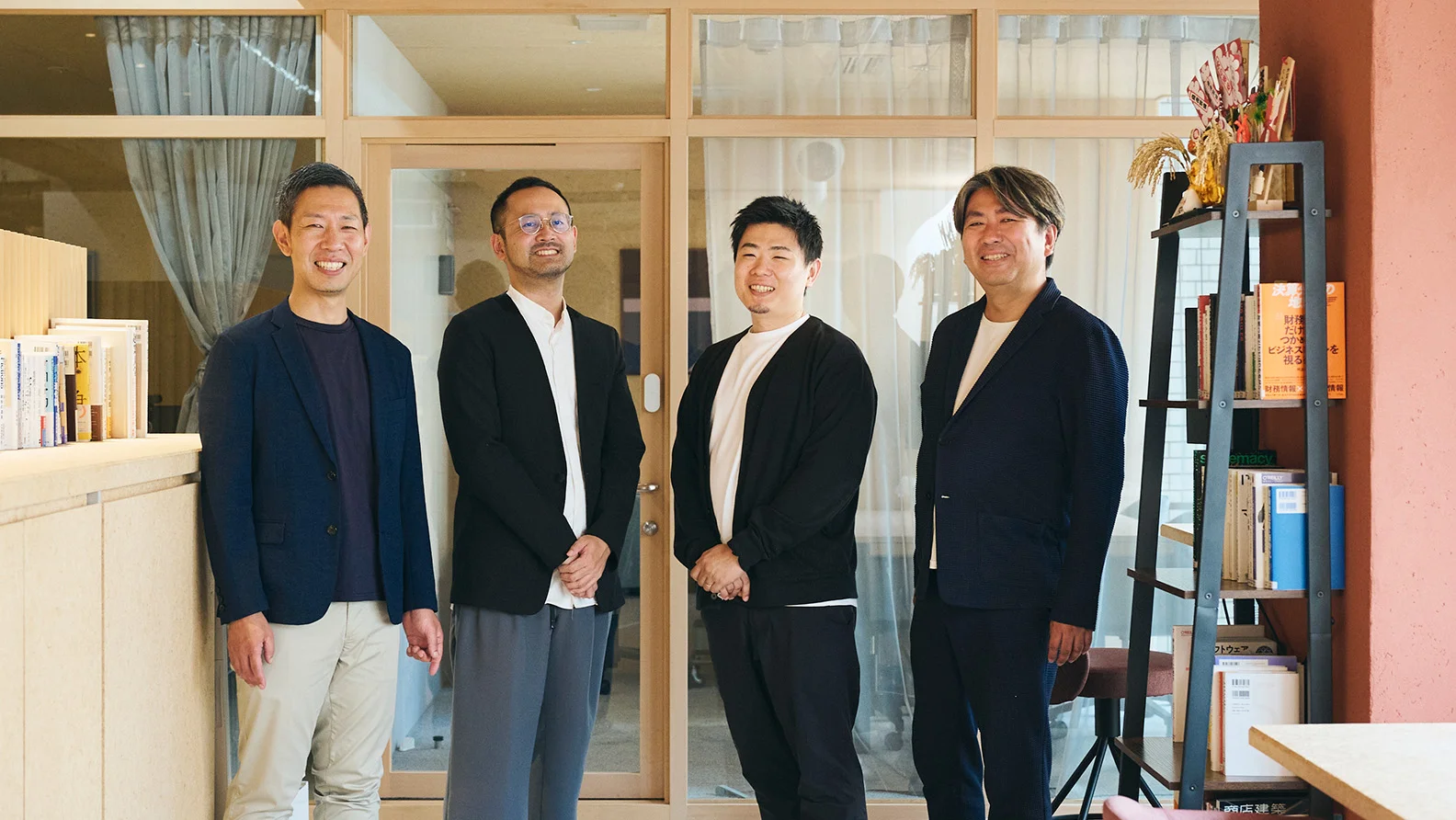専門性の高いフリーランスネットワークを武器にプロダクト開発を手掛けるGNUS社

遠藤:
今回の新ヘルスケアサービス立ち上げプロジェクト(以下、本プロジェクト)における貴社の役割について教えてください。
文分氏:
GNUSは電通グループの一員として、事業共創やプロダクト開発を支援している企業です。さまざまな案件を手掛けてきましたが、特に変革期にあるクライアントと共に事業の構想段階から手を動かしていくのが強みで、今回も構想初期のフェーズからプロジェクトに参画しました。
私はGNUSの代表という立場から、本プロジェクトを推進する担当として執行役員である三浦をアサインしています。
三浦氏:
私がプロジェクトに参画してからは、提案や体制づくり・開発・運用まで一気通貫で関わりました。弊社では「スタッフィング」と呼んでいるのですが、プロジェクトごとに最適なメンバーをフリーランスを含めて組成していくところから始め、サービスのリリース、保守運用まで、ほぼすべてを横断して担っています。
遠藤:
本プロジェクトでは、GNUS様が持つフリーランスネットワーク「GNUS Network」が活用され、最大50名体制で推進されていました。改めて「GNUS Network」についてお聞かせください。
文分氏:
一般的なフリーランス登録型のクラウドソーシングサービスとは異なり、私たちはプロダクト開発領域にフォーカスした専門性の高いフリーランスによるネットワークを構築しています。書類や面談による審査制を採用しており、コーディングに関するスキルだけでなくチームでの協働適性や成果品質へのコミットメントがあるかどうかも重要な基準です。合格率30%という厳格な事前審査を導入した結果、一定規模以上の開発会社でも難しいプロジェクトであっても対応できる、柔軟かつ専門性の高いチーム編成が可能になっています。
ただ、フリーランス同士が初対面に近い関係性でスタートするプロジェクトもあるため、価値観のズレやコミュニケーションの難しさといった側面があることは、私たちも課題として認識しています。
「企業を躍進させるための、なにかを」から始まったDXプロジェクト。GNUS社に求められた役割とは

遠藤:
本プロジェクトのきっかけをお聞かせください。
三浦氏:
クライアントからご相談いただいた当初は、新規事業の具体アイデアがない段階で、ざっくりとした「DXプロジェクト」としてスタートしました。クライアントは2名体制で、設立されたばかりのDX部署からは「今後の企業の躍進のためにやらねばならないことが多くあるが、何から着手すべきか分からない」というご相談をいただいていました。そこから何度も壁打ちを重ねる中で「リアルとデジタルを融合させた消費者向けの新しいヘルスケアサービス」という事業アイデアが浮かびました。
そこからアイデアが具体化され、「お客さまに求められるサービスや機能を集約したアプリを制作しよう」と意思決定され、2022年春ごろからプロジェクトが動き始めたのです。
遠藤:
本プロジェクトでクライアントが掲げていた目標をお聞かせください。
三浦氏:
「国内No1のヘルスケアビジネスを創出する」という目標を掲げていました。同時に「事業のPDCAを自社内で回す」という方針も掲げられていました。
そこで私たちに求められた役割は、自走可能な仕組みを構築しつつ、ナレッジやアセットをクライアントに残すこと、そして圧倒的な開発スピードで「新ヘルスケアサービス」の事業化を後押しすることでした。
変化するプロジェクトに求められたのは、高い視座を持つPM

遠藤:
本プロジェクトで貴社が抱えていた課題をお聞かせください。
三浦氏:
大前提として本プロジェクトはクライアントの最重要案件とも言えるプロジェクトであり、失敗は絶対に許されない状況でした。もちろんどんなプロジェクトであっても失敗は許されませんが、クライアントのご事情に鑑みて、より一層のリスク軽減の配慮をする必要がありました。
この中で大きな課題だったのが、クライアントとの要件調整と、開発メンバーのコントロールです。
クライアントの最重要案件ということもあり、現場担当者だけでなく、役員も強く関与する案件でした。しかも、消費者向けアプリということもあり、クライアントはユーザーの要望をしっかりと取り入れることを重要視していました。一方で、事業開始の期日は明確に定められていたため、期日を意識しつつも、一般的なアプリ開発よりも要件が流動的な状態で、開発を進める必要がありました。
役員・担当者含め、どう要件を調整・合意するか、また、変化する要件を期限がある中でどう優先度をつけて取り込むか、ここにとても労力が必要でした。
また、開発メンバーは50名ほどおり、メンバーのコントロールも大変でした。要件が変化する中で、スケジュールの変更もありました。この中で、メンバーに適切にタスクを持ってもらい、クオリティコントロールをするというのは、クライアントの要件調整だけでも大変な中、とても1人でできるような作業ではありません。
このような課題がある中で、スピーディーにプロジェクトを進めていくには、クライアントとの調整もでき、また開発メンバーを統括できるような高い視座をもった、プロジェクトマネージャーが必要です。
開発側とクライアント側で役割を分担する共創体制。JQが担った「統括PM」の立ち回りとは

下田:
今回のプロジェクトでは、GNUS様から6名のPMが参画し、フリーランスを中心とした約50名の開発体制が組まれました。弊社からは遠藤を含む2名が、6名のPMをまとめる「統括PM」のポジションとしてチームに参画させていただきました。私たちに期待していた役割を教えてください。
三浦氏:
プロジェクトは複数のサブチームから構成されており、アプリ開発やデザイン、データ整備、品質管理など各領域に専任PMを置きました。JQ社の統括PMには、この専任PMを監督し、プロジェクト全体を横断してのQCD管理やフェーズごとのタスク優先度を判断してもらいました。この統括PMの存在のおかげで、私はクライアントのフロントに立ち、刻一刻と変化する要望を汲み取りつつ、プロジェクトを着地させていく役回りに専念することができています。
遠藤さんにはチームマネジメントやプロジェクト全体のスケジュール進行、チームのコンディション管理に深く入っていただきましたね。
遠藤:
本プロジェクトは、不確実性が高く、かつ変動的でした。スケジュール変更も日常的に発生していたため、メンバーの心理的な納得感や信頼関係がとりわけ重要だったと感じています。
具体的には、通常のシステム開発プロジェクトよりもメンバーとの対話を増やすことを心がけました。GNUS Network所属のフリーランスの方はスキルフルで経験値も豊富ですが、多様なシステム開発経歴の持ち主が集まっていました。フリーランスと1on1の対話を通じて、背景事情の説明や期待値のすり合わせを行い、プロジェクトに対する温度感を調整していくよう心がけました。フェーズによっても上下しましたが、週に15件前後の1on1を行い、PMやエンジニア一人ひとりの状況や懸念を拾い上げ、アサイン調整や役割再編にも反映しました。
一方でPM陣の取りまとめでは、責任範囲を明確にすることを徹底しました。誰が、どの領域の責任を持ち、どこまで判断でき、どこからは統括PMの私が吸収するのかを明確にすることで、あいまいなボールが宙に浮くことを防いでいます。
対クライアント、対フリーランスで光る「先回り力」で、プロジェクトを無事に着地させられた

遠藤:
クライアントとの連携においては、どのような役回りを評価いただいていますか。
三浦氏:
開発のマネジメントだけでなく、クライアントとの合意形成でもJQさんの存在は大きかったです。たとえばスケジュールや進捗の見通しをクライアントと共有する際も、遠藤さんが用意してくれた資料の精度が高く、かつ分かりやすかったため、相手からの信頼も厚かったと思います。クライアントとのミーティングが1日3回、しかもすべて粒度の異なるアジェンダが同時進行していた中でも、整理された情報でスムーズに議論ができたのは、JQさんのサポートのおかげです。
遠藤:
弊社のプロジェクトマネジメントで印象に残っている要素をお聞かせください。
三浦氏:
開発とクライアント連携の両方で感じたのは「先回り力」です。まず開発側では、各サブシステムを全体としてはウォーターフォール的に進めつつも、クライアントの要望の変化にあわせて、アジャイルに開発する必要があるという状況の中で進捗を緻密に把握し、どこがボトルネックになりそうか、どこを先に動かすべきかと日々判断し、先回りしていたと思います。
クライアント向けでは、典型的なグリップ型のマネジメントではなく、期待値やゴールの調整で先回り
していました。進捗や課題に対してすり合わせを重ね、最後の最後でひっくり返されないようなコミュニケーションに努めていたと思います。さらにサービスの特性上、常に消費者の声がダイレクトに経営判断へ反映される文化だったため、大きな変化を前提にした運用体制でもあったと思います。
遠藤:
弊社のプロジェクトマネジメントで印象に残っている要素をお聞かせください。
三浦氏:
リリース直前の、より一層重要で迅速な判断が求められる局面では、遠藤さんが毎日のように弊社に出社いただけたことが何より嬉しかったです。クライアントや社内チーム、外部のフリーランスを含めて、誰をどこの役割に充てるか、その場で意思決定ができました。また、フリーランスのスタッフィングも現場でリアルタイムに調整できたことで、最後の局面でチームが崩れずに完走できたのは、遠藤さんのご尽力のたまものです。
本来2年はかかるであろうプロジェクトを6ヶ月で完遂

遠藤:
今回のプロジェクトの成果についてお伺いできればと思います。最終的には、新ヘルスケアサービスのスマートフォンアプリと、会員登録のWebシステム刷新を期日通りにリリースできました。
三浦氏:
要望もプロジェクト全体も日々変わっていく中で、アプリとWebの両方をなんとかリリースまで持っていけたこと自体、大きな成果だと思います。チームのエンジニアからも「これは間に合わないだろう」という声もあるなかで、プレッシャーはとても大きいものでした。
このプロジェクトを普通に進めればおそらく2年はかかると思いますが、それを6か月で完遂させました。開発コストを抑えながら4倍速で走りきった感覚ですね。
遠藤:
品質面でもユーザーからの評価は高く、継続的な改善プロセスも構築させていただきました。
三浦氏:
リリース後も1年間ほどは毎週のようにカスタマーサクセス、マーケ、開発チームが一丸となって、ユーザーの声に即応するスクラム体制を組んでいました。SNSの投稿ひとつから議論を始め、数日でアップデートを出すという対応を続ける中で、開発メンバーもどんどん当事者意識を持って動いてくれるようになったと思います。
クライアント側にも変化がありました。当初は2名だけのDX部署が、いまや120名規模にまで拡大したそうです。当初から、デジタルとデータを活用した仕組みの構築とインハウス化を最終的なゴールとして描かれていましたので、クライアント側で自ら課題を見つけて改善に取り組める体制になったのは、プロジェクトとして最も大きな成果だと感じています。
また、プロジェクトに参加されたフリーランス一人ひとりにも得られた学びやナレッジがあったことと思います。プロフェッショナルな人材がプロジェクトを乗り越えて成長し、次のプロジェクトに活かされることも「GNUS Network」の強みです。そして何より、世の中の誰もが知るサービスの立ち上げに関わり、そして成功に導いたという経験は、何にも代えがたい誇りになったと考えています。
「BtoCのプロダクト開発の極み」で得られた学びを活かし、今後のプロジェクトにつなげたい

遠藤:
今回のプロジェクトを受け、今後の展望をお聞かせください。
三浦氏:
今回のプロジェクトを無事に乗り越えたことで、どんなプロジェクトでも対応できる自信が得られました。特に今回のような消費者向けの新規事業プロジェクトでは、KPIの定義すら難しい場面が少なくありません。たとえサービスがリリースされても、多くの人に受け入れられるかは別問題であり、開発・運用以外にもマーケティングやクリエイティブの総合力が問われます。
そうした文脈で、今回のプロジェクトはまさに「BtoCのプロダクト開発の極み」であり、その中でPMとしてどう思考し、どう行動すべきかという視点で多くの学びがありました。この学びは、確実に今後のプロジェクトに活かされていくものと思います。
下田:
最後に読者へのメッセージをお願いします。
文分氏:
JQ社はもともとプロジェクトマネジメントスキルが非常に高いと感じています。BtoBでは予見可能性の高いプロジェクトが多い一方、BtoCは次々と仕様や要件が変わる“波”のような世界観ですが、JQ社のプロジェクトマネジメントはそのどちらにも対応できる、稀有な存在です。
今回のような変動の激しいプロジェクトでも、冷静に全体を俯瞰しながら、ステークホルダーと密に連携し、最適な判断を続けてくれました。領域を問わず、プロジェクトを前に進める頼れるパートナーとして、プロジェクトマネジメントに悩む企業にはぜひおすすめしたいですね。
下田:
ありがとうございました。