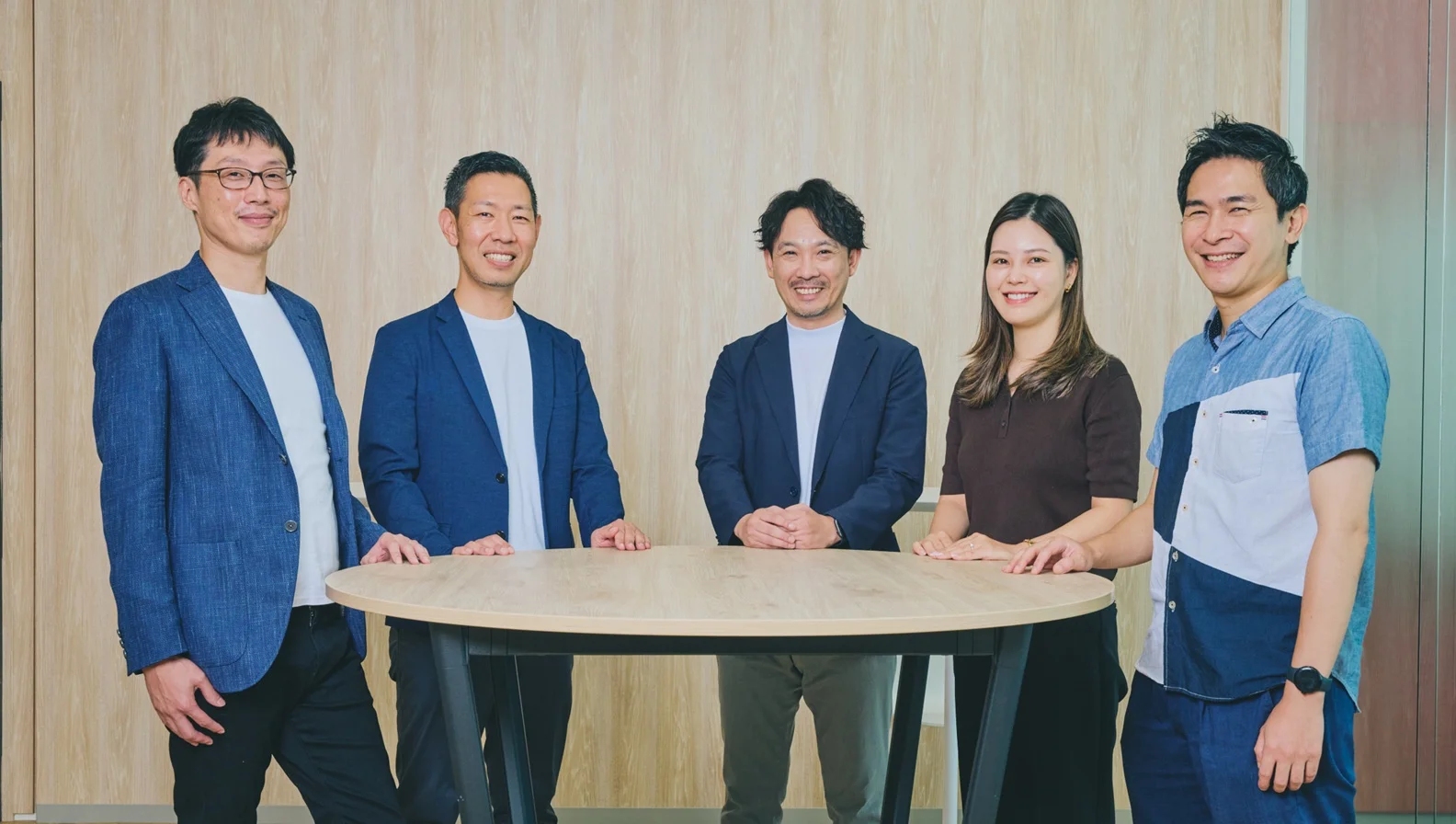マルチベンダーをとりまとめ、生活者や従業員体験の向上に挑む。電通社のプロジェクトマネジメントと体制とは

飯田:
プロダクトマネジメント部のミッションや業務内容についてお聞かせください。
高橋氏:
プロダクトマネジメント部では、クライアントさまのシステム導入をご支援することを主業務としています。単なる開発のデリバリーにとどまらず、ビジネスゴールを正しく理解し、生活者や従業員の体験を豊かにするシステム基盤の開発をマネジメントしていくことが大きなミッションです。
開発案件の規模は数千万円規模から二桁億規模まで幅広く存在し、ステークホルダーもクライアントさまを含め、多いときには5社以上に及びます。電通グループ内だけでなく、外部パートナーとの協業が多いため、プロジェクトマネジメントには高度な調整力が求められます。2025年8月現在、プロパー社員だけでなくSIer出身の社員など13名が在籍し、さまざまな経験を積んできました。
堀田氏:
私は新卒でSIerに入社し、数年間PMとしての経験を積んだ後にプロダクトマネジメント部に所属しました。前職のSIerでは、開発工程が社内でほぼ完結していたのに対し、プロダクトマネジメント部では複数のベンダーをマネジメントする点が、大きな違いと感じます。また、クライアントさまのカウンターパートもシステム部門ではなく、マーケティング部門のお客さまと向き合うことが多いため、技術に詳しくない方にも分かりやすく伝える力が重要であると感じています。
西氏:
堀田とは違い、私はプロパーとして入社しました。社内の情報システム部門でシステム開発を担い、その後に広告営業やメディア買付などを経験した後、現在のプロダクトマネジメント部に所属しています。現在は主に開発マネジメント領域を担当し、クライアントさまのサービス開発支援を中心にプロジェクトマネージャーの役割を担っています。外部でのPM経験はありませんが、社内開発案件を通じて知見を積み重ねてきました。
下田:
一般的なSIerは、プロジェクトを自社内で統制をとって進められるのに対し、電通様は、多様なグループ会社や外部パートナーを巻き込みながらプロジェクトを進める必要があります。各社は強みが異なり、またSIに関する前提知識、経験もばらばらです。この中でスケジュールを切って、全員の理解と歩調を合わせながら推進していくことは非常に難易度が高い作業だと思います。
クライアント・ベンダーごとに異なる前提知識・経験。社内のPMスキルのばらつきにも課題感

飯田:
プロダクトマネジメント部では、プロジェクトマネジメントの理想像についてどのようにイメージしているのでしょうか。
高橋氏:
我々が担う案件は規模が大きく、関わるステークホルダーも多いという特徴があります。そのため、より高いクオリティのデリバリーを、個人の力量に依存するのではなく、いかに標準化して提供できるかが重要です。もちろんディレクター層のサポートもありますが、仕組みやノウハウを型化することで、プロジェクト全体でQCDを意識した運営を行えている状態を理想としていました。また、プロジェクトマネジメントを標準化できていれば、万が一のトラブル発生時にも共通の型を活用し、メンバー同士が迅速にサポートできる点も大きな価値だと考えています。
飯田:
プロダクトマネジメント部が抱えていた、プロジェクトマネジメントにおける課題をお聞かせください。
高橋氏:
SIer出身、プロパー社員、事業会社の情報システム出身など、我々の部署は多様なバックグラウンドを持つ人材が集まっており、それ故に各自の前提知識・スキルがばらばらでした。それ自体は、多様なプロジェクトに対応できるという点で大きな強みですが、ベースとなるプロジェクトマネジメント知識・スキルは共通化する必要があると考えました。
堀田氏:
私自身、前職のSIerでは基幹システムのような案件を多く担当していましたが、電通では顧客接点に近い開発案件が多く、同じ“プロジェクトマネジメント”でも求められるスタイルが違うと感じています。基幹システムと生活者と接点があるソリューションでは、PMにとって必要となる視点も異なります。そのため、自分のやり方を一度見直し、電通版の“プロジェクトマネジメント”にアップデートしたいと強く思っていました。
西氏:
クライアントさまによって使う言葉や前提が異なることも課題に感じていました。複数社を巻き込むプロジェクトの場合、まず私たちがプロジェクトマネジメントを共通化し、プロジェクトメンバーに正しくインプットする必要がありました。認識のずれが後々大きなトラブルに発展することもあるため、言葉や考え方のギャップを調整し、合意形成を図ることは非常に重要です。
飯田:
電通様の案件は、基幹システムほどは、堅牢さが求められませんが、小規模案件ほど柔軟には進められない、という特徴があると思います。いわばハイブリッドな案件が多い中で、電通様らしいマネジメント手法と具体的なティップスが求められていたように感じました。過去に携わられてきたさまざまな案件の最大公約数を模索し、共通言語に落とし込んでいく取り組みは、多様なバックグラウンドを持つ電通様のPMの皆様が、クライアントさまと新しい価値を共創するための土台となると思います。
知識と経験を接続し、脱属人化するための仕組み。実践的なケーススタディが受講の決め手に

飯田:
今回、実践プロジェクトマネージャー育成研修を受講いただく以前には、プロジェクトマネジメントスキルの共通化に向けた取り組みをされてきたのでしょうか。
高橋氏:
システム開発をはじめ大型案件が増える中で、ディレクター層を中心にチェックリストや提案書・計画書の型化を進めてきました。一定の品質担保と再現性の向上といった手応えはあったものの、プロダクトマネジメント部の多様なバックグラウンドを持つメンバーへ「共通のプロジェクトマネジメントスキル」を浸透させるには限界があり、包括的であり、座学と実務を接続する実践的コンテンツが必要だと感じていました。
飯田:
数ある選択肢の中から、最終的にJQの「実践プロジェクトマネージャー育成研修」を選定いただいた決め手を教えてください。
高橋氏:
過去、複数プロジェクトでJQ社と協業する中で印象的だったのが、我々と同じ発注者側に近い立場でマルチベンダーを統合し、QCDが変動する局面でも着実に合意形成を積み上げていく姿です。こうした立ち位置とスタンスが、これまで抱えてきた課題感にフィットしていると確信したこと、さらに過去・現在進行系のJQ社との協業案件を「生のケーススタディ」として活用できる点から、座学で終わらずに実務へ即転用できる研修が可能だと判断したことが決め手となりました。
堀田氏:
SIer時代の初期研修では、ベースとなる簡単な基礎知識を学んだ後は、現場でOJTを繰り返し、配属された部署ごと、プロジェクトごとのやり方を学んでいく傾向が強かったと思います。一方でJQ社の研修は、包括的な座学がありながらも、実案件のティップスもふんだんに織り込まれているので、「どの局面で何を意思決定し、どう合意を形成するか」を自分ごととして咀嚼できる点に魅力を感じました。
西氏:
私の場合、プロジェクトマネジメントスキルはすべてOJTで学んだため、体系的に学習する機会が乏しかったと思います。工程全体でQCDをいかに管理し、リスクや品質をどこまでの粒度でチェックするかを、自身の思考プロセスや経験と照らし合わせながら再整理することを、JQ社の研修に期待していました。
下田:
大手SIerでは、ビジネスの特性上、社員が同じ事業部・同じ案件に長期にわたって所属することが多く、どうしてもその事業部・案件に適したやり方を教育するという傾向にあると思います。結果としてOJT偏重に陥りやすいのではないでしょうか。
飯田:
私が以前所属していた大手SIerでも、プロジェクトマネジメントに関する研修は多数準備されていたものの、受講コンテンツやタイミングは個人に委ねられており、キャリア形成を見据えた体系的な研修という意味では人材育成や組織管理といったラインマネジメント色の強い研修を重要視していると感じました。たとえば管理職研修と呼ばれるような研修です。そのため、適切なタイミングで実践的なプロジェクトマネジメントスキルを学ぶとなるとOJTに偏らずを得ないのだと思います。
全55プログラム中13を厳選。型化と実際のケーススタディを両立し、即時に現場へ適用できた

飯田:
2024年12月頃から約3ヶ月にわたり、リモート形式で集中的に研修を実施させていただきました。通常業務との両立や受講体制、対象者の選定方針など、運営面のポイントを教えてください。
高橋氏:
受講するメンバーは日々それぞれの案件にアサインされているため、数ヶ月前から1講義2時間の枠を全員分まとめて確保しました。定例会議を避けつつ、全11回分の講義を受講できる時間をカレンダー上でブロックしたことで無理なく参加できるように工夫しています。受講者はプロダクトマネジメント部の実務担当6名に絞って、プロジェクトマネジメントの体系的な理解に基づくベースアップに集中しました。
西氏:
定例や緊急対応とぶつからないよう事前に社内外のスケジュールを調整いただけたこと、また事前課題を重くしすぎないプログラム設計だったことが、研修の負荷を抑えつつもプロジェクトマネジメントの理解を深められたポイントだったと思います。
また、在宅と出社を問わずできるオンライン講義形式は、とても実務フレンドリーでした。このおかげで、全11回の講義を欠席なく走り切ることができています。
下田:
カリキュラムの構成では、全55プログラムの中から必要そうな13プログラムを選定いただき、11コマに圧縮、編成させていただきました。
まず「開発プロセス全体像」を俯瞰しつつ、企画・構想や要件整理といった最上流をしっかり押さえること、さらに非SIer出身の社員の皆様にも単体・結合・総合などテスト工程の実務イメージを持っていただくことを柱に据えました。加えて、計画立案と、進捗・課題・品質・変更それぞれの管理業務における実践的な押さえどころをインプットできるようにしています。
飯田:
電通様のニーズを踏まえ、「あるべき計画」と「品質の作り込み」を実務で再現できるように工夫させていただきました。我々の型を提示しながらも、生のケースを題材として、「どの局面で何を決め、どう合意を形成するか」を議論できるように設計しています。
今回のプログラムで、特に効いたと感じる学びや、現場での適用例があれば教えてください。
堀田氏:
正攻法を理解したうえで、事前に進め方のコンセンサスが取れていたとしても、現実的にその進め方が難しいという局面で、どうアジャストしていくか、といった“引き出し”を増やすことができました。
西氏:
クライアント側の担当の方は情シス以外の部門であることが多いため、例えば、各工程のゴール感についての前提をすり合わせる必要がありますが、この研修の受講後は、各工程で「いつまでに何を決めるか/どの状態を目指すか」という型を提示しやすくなりました。型を持ち、使い方を理解することで、電通側だけでなくクライアント様とも、再現性のあるプロジェクトの進め方のノウハウを蓄積できていると感じます。
ドキュメント品質を底上げし、炎上を未然に防ぐ。不確定要素をつぶし、的確な合意形成でプロジェクトを安定化

飯田:
実践プロジェクトマネージャー育成研修を通じて、どのような成果が得られましたか。
高橋氏:
最も大きな成果は、プロジェクトマネジメントの手法やプロセスをひとつの型として組織内に浸透させることができた点です。これによって各メンバーが携わる案件を同じ考え方で進行できるようになり、ディレクター陣としてもプロジェクトごとの進捗や課題に対して同じ視点でサポートが行えるようになりました。たとえば、ステークホルダーとの合意形成や品質確保といった重要なプロセスにおいて、研修で学んだ型を共通言語として議論できるようになったことで、支援のスピードや精度が向上していると感じています。
西氏:
以前と比べて、炎上を未然に防げているように感じています。これまでは初期の不確定要素がプロジェクトの進行とともに炎上へ発展するケースもありましたが、今回の研修によって事前にリスクを把握し、合意形成まで進められるようになったことで、炎上する前に封じ込められるようになりました。
堀田氏:
私自身の実感としては、各フェーズで作成するドキュメントのクオリティが明らかに向上しました。これまでは経験則や他案件の踏襲でドキュメントを作成することも多かったのですが、研修で「最低限、この成果物ではここまで記述すべき」という基準を学べたことで、ドキュメント品質を標準的にチェックできるようになり、結果としてクオリティのベースラインが引き上げられたと思います。
下田:
研修後に加わった新規メンバーの方には、どのように研修内容を展開されているのでしょうか。
高橋氏:
研修後にキャリア採用で複数の新メンバーがチームに加わっております。彼らに対しても、今後、この研修を提供する仕組みを検討しています。
飯田:
研修後、協業中のプロジェクトで感じた変化として、計画と実行のギャップを検知する力が強くなったと感じます。現在私がご一緒しているプロジェクトのメイン担当の方は、もともと細かく案件を見られる方でしたが、研修を経てその精度がより高まり、遅れの兆候を早い段階でアラートし、クライアントやベンダーへ迅速に働きかけされています。こうした行動の変化は、単なる知識習得にとどまらず、プロジェクトマネージャーとしての推進力を一段押し上げた結果といえるのではないでしょうか。
プロジェクトマネジメントの実践と、ホリスティックな視点で企業の基盤変革を支援していく

飯田:
今後の展望について、プロダクトマネジメント部全体ではどのような方向性を描いてるのでしょうか。
高橋氏:
我々が所属しているビジネス・トランスフォーメーション局(BX局)は、事業変革・企業変革の課題をホリスティック、つまり全体論的に捉え、クライアントさまの持続的な成長を支援することをミッションとしており、そのために「Holistic Transformation Model」というフレームワークを採用しています。その中でも私たちの部門が担っているのは企業基盤変革とシステム構築の領域であり、この領域はAIなどの新しい技術の登場により開発手法やプロジェクトのプロセスがますます複雑化しているのが現状です。
だからこそ、今回のプロジェクトマネジメント研修で得た型や知見というベースが重要になると思っています。様々なプロジェクトにアジャストしながら、この「Holistic Transformation Model」を実践的に推進し、クライアント企業の変革を力強く後押ししていきたいと考えています。
飯田:
そうした文脈で、これまでJQというパートナーを今後どのように位置づけ、どのような期待を寄せていますか。
高橋氏:
今回ご提供いただいた研修コンテンツを活用させていただくことはもちろん、これまで数多くのプロジェクトで協業させていただいた経験からも、今後さらにさまざまな案件でもご一緒できればと考えています。
特に現在私たちが取り組んでいるのは、複数の開発ベンダーを束ねるマルチベンダー体制のプロジェクトが多く、コントロールや調整が格段に難しくなっているのが実情です。そのような場面で、JQ社と共にステークホルダーを巻き込みながらプロジェクトを推進していければ、より大規模な課題にも立ち向かえると期待しています。
飯田:
同じくプロジェクトマネジメントに課題を抱える企業に向けて、私たちの研修はどのような価値を提供できるとお考えでしょうか。
高橋氏:
システム開発に直結する案件に携わる企業はもちろん、多くの企業活動においてプロジェクト単位で仕事が進んでいくのは日常的なことです。すべてのプロジェクトに関わる企業や人材にとって、JQ社の実践プロジェクトマネージャー育成研修は有用だと考えています。プロジェクトには必ず不確実性が伴いますが、それを回避し、成功確率を高めるための手法やプロセスを学べる点は、あらゆる業種にとって大きな価値があるはずです。